子供の視力は親から遺伝してしまうのか。そのことについて詳しく解説しているページになります。
投稿日:2025年07月11日
最終更新日:2025年07月16日
最終更新日:2025年07月16日
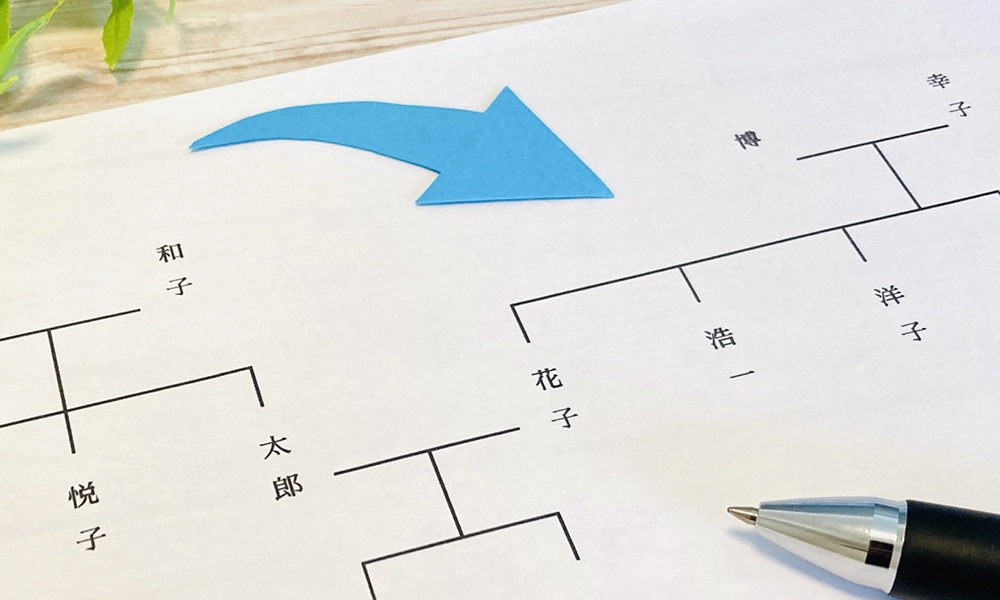
子供の視力に対する不安は、現代の親たちにとって非常に身近で切実な問題です。テレビやスマートフォン、タブレットなどのデジタル機器が生活に浸透し、小学生の近視率が年々増加しています。
実際、文部科学省の統計によれば、視力1.0未満の小学生の割合はすでに4割を超え、都市部ではそれが半数以上にのぼるといった報告もあるほどです。
また視力の問題が身近になるにつれて、特に両親とも近視の場合、子供にも遺伝して視力が低下してしまうのではないかという心配をする親も増えています。
確かに人間の身体の状態はその一部を親からの遺伝で引き継ぐものであり、親の視力が低いと子供も視力が落ちやすいというデータも存在します。
視力と遺伝の関係については、これまで数多くの研究が行われてきました。
たとえば、片方の親が近視であれば遺伝によって子供の近視リスクは約2倍、両親ともに近視の場合はその確率が約5倍に跳ね上がるという研究結果も存在します。
しかしいっぽうで、視力低下の原因は遺伝が全てではありません。むしろ視力低下の理由は生活の中に多数存在し、遺伝の影響というのはごく一部にすぎません。
実際、同じ親から生まれた兄弟姉妹でも、視力に大きな差が出ることは珍しくありません。こうした違いが生じる背景には、遺伝以外の生活習慣や環境要因が密接に関係していることが挙げられます。
親として必要なのは遺伝の心配をすることではなく、子供が過ごす日常の中にある目への負担や、視力にとって良くない習慣に気づき、早めに改善していくことなのです。
では親として子供の視力低下を予防するために、具体的にどのような取り組みができるのでしょうか。生活の中にある視力の差がつく原因について詳しくお話していきます。
もっともわかりやすく、改善しやすいのは近距離作業の改善でしょう。近年ではスマートフォンやパソコンが子供にも身近なものなりました。
学校の勉強に加え、家でも近距離で長時間物を見ることが増えて、目に負担がかかっているのです。
またデジタル機器は画面から発するブルーライトの光により目に多くのダメージを与えてしまうため、読書や勉強よりも目に与える影響が大きいです。
これらの事実から、デジタル機器の使用時間を制限することが推奨されます。1日1~2時間程度に制限できるのが理想ですが、授業でタブレットを使用する学校も増えています。
全体の時間制限が難しい場合は、適度に小休憩を入れ、意識的に画面から目を離して遠くを見る時間を作るようにしてください。
さらに、外遊びできる場所が減り、室内で遊べる玩具も増えたことで外遊びの時間が減ったことも近年の子供たちの視力低下の要因になっています。
屋外で自然光を浴びる時間が不足すると網膜にあるドーパミンの分泌が抑制され、眼軸が伸びやすくなり、近視が進行しやすくなるという生理的メカニズムが指摘されています。
1日1時間以上は外で遊ぶことが推奨されますが、難しい場合にはできるだけ休日に家族で外に出て過ごす時間を作り、子供が自然光を浴びられるようにしてあげてください。
また室内で過ごす時間が増えることで、室内の照明が目に与える影響も大きくなっています。特に本を読んだりゲームをする時など近距離作業時は、暗すぎても明るすぎても負担が大きくなります。
合わせて、姿勢も気を付けてみてください。姿勢が悪いと画面やノートと目の距離が近くなりすぎてしまいます。
さらに近すぎると自分自身の影で見ている部分を暗くしてしまう場合もあり、ますます負担が大きくなり、目を酷使してしまう原因になるのです。
子供が勉強や読書、ゲームなど近距離作業をしている時は作業時間に加えて姿勢や明るさも注意してみておく必要があります。
これらの要因は日常の中に自然と存在しているため、特別なことをしていなくても、気づかぬうちに視力を悪化させてしまっているケースも少なくありません。
したがって、子供の視力を守るには、親がこうした生活環境に目を向け、できるところから改善していくことが非常に重要なのです。
こうした日常の工夫に加えて、半年~1年に1度は眼科での検診を受けることも欠かせません。
子供自身が視力の変化に気づかない場合も多いため、客観的な診断によって早期発見・早期対応を図ることが必要です。
最近ではオルソケラトロジーや低濃度アトロピン点眼といった近視の進行を抑制する医療的手段も登場しており、必要に応じて専門医と相談しながら検討することが推奨されます。
また、視力検査の結果だけに頼らず、日々の様子をよく観察し、「目を細めて物を見る」「頭を傾けてテレビを観る」「読書の距離が近すぎる」などのサインに早めに気づくことも、早期発見につながります。
特に小学生の頃は視力が急激に変化しやすい時期であり、この段階で正しい対策を講じるかどうかが、将来的な視力障害を防ぐカギとなります。
近視は一度進行すると回復が難しいとされているため、「気になったらすぐ行動する」ことが何よりも重要なのです。
また定期健診と合わせて行いたいのが、目の疲労を溜めないようにすることです。それには先ほどお話したような近距離作業の時間制限やこまめな休憩のほか、目の疲れを解消させる方法を実践することです。
目の疲れを解消させるには十分な休息や簡単なストレッチのほか、血行促進や目のピント合わせを担う筋力をほぐすことができる「目リライト」に行くのがお勧めです。
「目リライト」は目の周辺にある深層筋肉、毛様体筋に適切な刺激を与えることで血行を促進し、筋肉の緊張をやわらげ、コリを解消することができます。
毛様体筋が緊張し消耗していると目のピント調整能力が衰え、一時的な近視となります。この状態が長く続くと一時的ではない近視に繋がってしまいます。
そのため「目リライト」で目の疲れを解消することは視力低下を防ぎ、目の健康を守るのに大きく役立つのです。
「目リライト」はHPで簡単に予約することができますので、子供の目の健康が気になる親御さんはまず一度試してみることをおすすめします。
実際、文部科学省の統計によれば、視力1.0未満の小学生の割合はすでに4割を超え、都市部ではそれが半数以上にのぼるといった報告もあるほどです。
また視力の問題が身近になるにつれて、特に両親とも近視の場合、子供にも遺伝して視力が低下してしまうのではないかという心配をする親も増えています。
確かに人間の身体の状態はその一部を親からの遺伝で引き継ぐものであり、親の視力が低いと子供も視力が落ちやすいというデータも存在します。
視力と遺伝の関係については、これまで数多くの研究が行われてきました。
たとえば、片方の親が近視であれば遺伝によって子供の近視リスクは約2倍、両親ともに近視の場合はその確率が約5倍に跳ね上がるという研究結果も存在します。
しかしいっぽうで、視力低下の原因は遺伝が全てではありません。むしろ視力低下の理由は生活の中に多数存在し、遺伝の影響というのはごく一部にすぎません。
実際、同じ親から生まれた兄弟姉妹でも、視力に大きな差が出ることは珍しくありません。こうした違いが生じる背景には、遺伝以外の生活習慣や環境要因が密接に関係していることが挙げられます。
親として必要なのは遺伝の心配をすることではなく、子供が過ごす日常の中にある目への負担や、視力にとって良くない習慣に気づき、早めに改善していくことなのです。
では親として子供の視力低下を予防するために、具体的にどのような取り組みができるのでしょうか。生活の中にある視力の差がつく原因について詳しくお話していきます。
もっともわかりやすく、改善しやすいのは近距離作業の改善でしょう。近年ではスマートフォンやパソコンが子供にも身近なものなりました。
学校の勉強に加え、家でも近距離で長時間物を見ることが増えて、目に負担がかかっているのです。
またデジタル機器は画面から発するブルーライトの光により目に多くのダメージを与えてしまうため、読書や勉強よりも目に与える影響が大きいです。
これらの事実から、デジタル機器の使用時間を制限することが推奨されます。1日1~2時間程度に制限できるのが理想ですが、授業でタブレットを使用する学校も増えています。
全体の時間制限が難しい場合は、適度に小休憩を入れ、意識的に画面から目を離して遠くを見る時間を作るようにしてください。
さらに、外遊びできる場所が減り、室内で遊べる玩具も増えたことで外遊びの時間が減ったことも近年の子供たちの視力低下の要因になっています。
屋外で自然光を浴びる時間が不足すると網膜にあるドーパミンの分泌が抑制され、眼軸が伸びやすくなり、近視が進行しやすくなるという生理的メカニズムが指摘されています。
1日1時間以上は外で遊ぶことが推奨されますが、難しい場合にはできるだけ休日に家族で外に出て過ごす時間を作り、子供が自然光を浴びられるようにしてあげてください。
また室内で過ごす時間が増えることで、室内の照明が目に与える影響も大きくなっています。特に本を読んだりゲームをする時など近距離作業時は、暗すぎても明るすぎても負担が大きくなります。
合わせて、姿勢も気を付けてみてください。姿勢が悪いと画面やノートと目の距離が近くなりすぎてしまいます。
さらに近すぎると自分自身の影で見ている部分を暗くしてしまう場合もあり、ますます負担が大きくなり、目を酷使してしまう原因になるのです。
子供が勉強や読書、ゲームなど近距離作業をしている時は作業時間に加えて姿勢や明るさも注意してみておく必要があります。
これらの要因は日常の中に自然と存在しているため、特別なことをしていなくても、気づかぬうちに視力を悪化させてしまっているケースも少なくありません。
したがって、子供の視力を守るには、親がこうした生活環境に目を向け、できるところから改善していくことが非常に重要なのです。
こうした日常の工夫に加えて、半年~1年に1度は眼科での検診を受けることも欠かせません。
子供自身が視力の変化に気づかない場合も多いため、客観的な診断によって早期発見・早期対応を図ることが必要です。
最近ではオルソケラトロジーや低濃度アトロピン点眼といった近視の進行を抑制する医療的手段も登場しており、必要に応じて専門医と相談しながら検討することが推奨されます。
また、視力検査の結果だけに頼らず、日々の様子をよく観察し、「目を細めて物を見る」「頭を傾けてテレビを観る」「読書の距離が近すぎる」などのサインに早めに気づくことも、早期発見につながります。
特に小学生の頃は視力が急激に変化しやすい時期であり、この段階で正しい対策を講じるかどうかが、将来的な視力障害を防ぐカギとなります。
近視は一度進行すると回復が難しいとされているため、「気になったらすぐ行動する」ことが何よりも重要なのです。
また定期健診と合わせて行いたいのが、目の疲労を溜めないようにすることです。それには先ほどお話したような近距離作業の時間制限やこまめな休憩のほか、目の疲れを解消させる方法を実践することです。
目の疲れを解消させるには十分な休息や簡単なストレッチのほか、血行促進や目のピント合わせを担う筋力をほぐすことができる「目リライト」に行くのがお勧めです。
「目リライト」は目の周辺にある深層筋肉、毛様体筋に適切な刺激を与えることで血行を促進し、筋肉の緊張をやわらげ、コリを解消することができます。
毛様体筋が緊張し消耗していると目のピント調整能力が衰え、一時的な近視となります。この状態が長く続くと一時的ではない近視に繋がってしまいます。
そのため「目リライト」で目の疲れを解消することは視力低下を防ぎ、目の健康を守るのに大きく役立つのです。
「目リライト」はHPで簡単に予約することができますので、子供の目の健康が気になる親御さんはまず一度試してみることをおすすめします。
「目リライト」はこちらから

