子供の視力検査はいつ受けるべきかお伝えしています。
投稿日:2025年05月20日
最終更新日:2025年05月21日
最終更新日:2025年05月21日
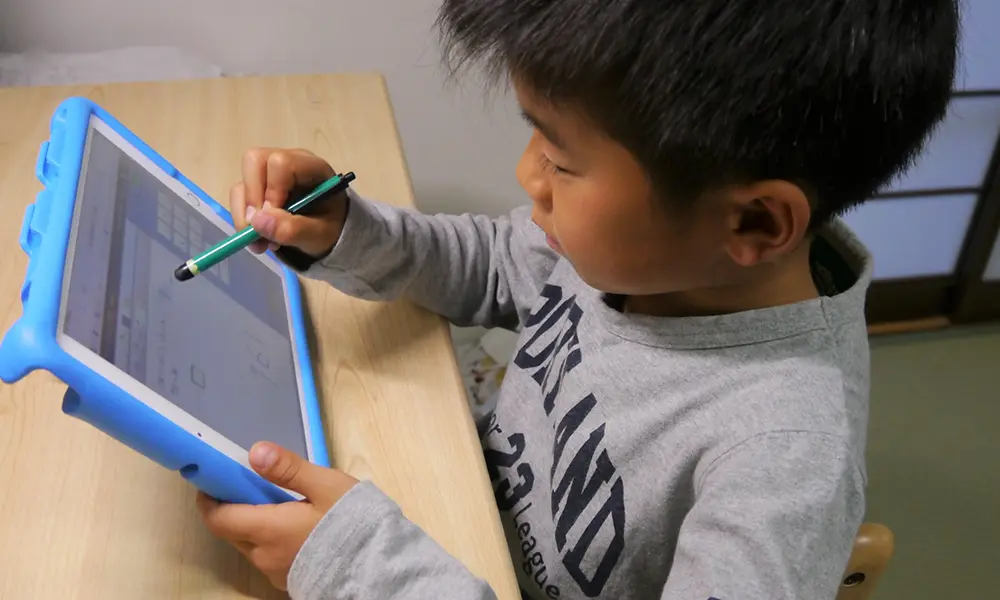
子供の目は、日々の成長とともに大きく発達します。この大切な視力の発達を見守るために、大人がすべきことのひとつが「視力検査のタイミング」を正しく理解し、適切な時期に受けさせることです。
日本の子供たちが受ける視力検査は、一般的には幼稚園・保育園、小学校、中学校での定期健康診断の一環として年に1回行われています。
これは文部科学省の定める学校保健安全法に基づくもので、視力低下の兆候を把握するための第一歩です。
しかしながら、この年1回の視力検査だけで安心するのは早計です。視力は急激に変化することがあり、特に成長期の子供は短期間で大きく低下することもあります。
学校での視力検査では異常を完全に把握することは難しく、検査の形式や時間の都合上、軽度の症状は見逃されるケースも少なくありません。
そのため、親が日常生活の中で子供の様子を観察し、必要に応じて家庭でのチェックや専門医による検査を受けさせる判断が必要不可欠です。
たとえば、黒板の文字が見づらいと訴えたり、テレビに異常に近づいて見たりする行動は、視力低下のサインかもしれません。
また、目を細めて本を読んだり、片目を手で隠して何かを見ようとしたりする仕草も、視力が落ちている可能性を示しています。
こうしたサインを見逃さず、すぐに視力検査を受けさせることで、症状の進行を防ぐことができます。
日本の医療機関では、子供向けの視力検査を随時受け付けています。小児科や眼科で簡単に検査を受けることができ、必要に応じて精密検査も可能です。
一般によく知られているランドルト環による視力検査だけでなく、小児用に特化した、子供でも答えやすい視力検査を行える眼科もあります。
多く見られるのは絵を利用した視力検査で、蝶々や鳥、犬など違いがわかりやすい動物の形のシルエットを出して、なんの動物かを当ててもらう方法です。
また、左右がおぼつかない子供でもランドルト環による視力検査が行えるよう、Cの形の道具を持たせ、それをランドルト環のCと同じ向きにしてもらうという方法もあります。
このように、眼科では小さな子供でもわかりやすい様々な手法が工夫され、実践されていますので、安心して医療機関に相談してください。
また、以下のようなタイミングでは特に、積極的に視力検査を受けさせることをおすすめします。
まずは、学校検診で「要再検査」や「1.0未満」と通知されたときです。
通知を見逃さず、すみやかに眼科を受診しましょう。学校検診では詳細な検査までは行われないため、診断が必要な場合があります。
テレビやスマホの画面を見る距離が極端に近いと感じたら、典型的な見え方悪化の兆候です。子供自身は見づらいと気づかないこともあるため、親の目が重要です。
「目が疲れる」「頭が痛い」などの訴えが増えたときも目が見えづらくなっている可能性があります。学習中や読書中にこうした症状がよく出る場合は、すぐに眼科での検査を受けることが重要です。
「たぶん大丈夫だろう」「もう少し様子を見よう」と先延ばしにせず、「気になるならすぐ眼科へ」が鉄則です。視力は一度悪くなると、回復に時間がかかるだけでなく、完全に元に戻らないこともあります。
兄弟姉妹や親が近視の場合も気を付ける必要があります。近視や遠視は遺伝的な影響で出やすさが変わるため、家族に近視や遠視、弱視などの傾向がある場合は、定期的な検査を習慣づけましょう。
入園、入学、進級など新しい生活環境になったときは、検査の良いタイミングです。
見えづらくなっていても子供自身では気づかず、またごく初期では子供の挙動にもあまり変化がなく親も気づきにくいことがあります。
ですので、生活スタイルが変化するタイミングを良い機会として、眼科での視力検査を受けることをおすすめします。
また、定期的な健診と合わせて、生活習慣でも注意が必要です。近視などが発症する原因の多くは、生活環境の中に潜んでいます。
現代の子供たちは、スマートフォンやタブレット、ゲーム機など、近距離での作業に多くの時間を費やしています。
こうした近距離作業が一因であることは、さまざまな研究でも明らかになっており、日本眼科医会でも注意を呼びかけています。
また、ゲームなどで室内の遊び時間が増えることに比例して外での遊びやスポーツの時間が少なくなることも、視力に悪影響を与える要因の一つです。
これらの問題に対して、親ができることはたくさんあります。
まずは、日常生活の中で子供の目の使い方に注意を払い、適切な距離で本を読む、明るい部屋で作業する、画面を見る時間を制限するなど、基本的な生活習慣の見直しを図りましょう。
また、1日1回は遠くを見せる時間を作るなど、目のリラックスにも努めることが効果的です。目を使う作業や遊びをしたあとは目を休ませることを習慣づけるのです。
特にスマホやタブレットは顔を近づけてしまいやすく、夢中になって長時間使用してしまいがちです。そのため、使用に家庭内ルールを設けることが重要です。
「1日○分まで」「30分使用したら10分休憩」といった時間管理は、目の健康だけでなく、生活全体のリズムを整えるうえでも効果的です。親自身がルールを守ることで、子供にも自然と習慣が身についていきます。
視力の問題は学業成績や集中力にも直結します。黒板が見えにくければ授業の理解が難しくなり、学習意欲の低下にもつながりかねません。
子供が安心して学べる環境を整えるためにも、目の健康維持はとても重要な項目なのです。
また、小学校高学年以降からは予習や復習など家での学習時間を増やしていくご家庭が多いです。同時に、目をどのように休ませるかをよりしっかりと考えていく必要がでてきます。
遠くを見るなど簡単な方法だけでなく、もう少し手をかけたホットアイマスクなどのセルフケアも取り入れると良いでしょう。
さらに効率的に目をしっかりと休ませるための方法として「目リライト」がおすすめです。
「目リライト」は目の周辺筋肉に適度な刺激を与え、目の酷使によって緊張してしまった筋肉のコリをほぐすことができます。
それによって目の疲れが回復し、疲れからくる一時的な見えづらさや頭痛なども解消され、目の健康を維持することができるのです。
「目リライト」はHP上で手軽に予約をすることができますので、子供の目の健康を守るためにも一度試してみることをおすすめします。
日本の子供たちが受ける視力検査は、一般的には幼稚園・保育園、小学校、中学校での定期健康診断の一環として年に1回行われています。
これは文部科学省の定める学校保健安全法に基づくもので、視力低下の兆候を把握するための第一歩です。
しかしながら、この年1回の視力検査だけで安心するのは早計です。視力は急激に変化することがあり、特に成長期の子供は短期間で大きく低下することもあります。
学校での視力検査では異常を完全に把握することは難しく、検査の形式や時間の都合上、軽度の症状は見逃されるケースも少なくありません。
そのため、親が日常生活の中で子供の様子を観察し、必要に応じて家庭でのチェックや専門医による検査を受けさせる判断が必要不可欠です。
たとえば、黒板の文字が見づらいと訴えたり、テレビに異常に近づいて見たりする行動は、視力低下のサインかもしれません。
また、目を細めて本を読んだり、片目を手で隠して何かを見ようとしたりする仕草も、視力が落ちている可能性を示しています。
こうしたサインを見逃さず、すぐに視力検査を受けさせることで、症状の進行を防ぐことができます。
日本の医療機関では、子供向けの視力検査を随時受け付けています。小児科や眼科で簡単に検査を受けることができ、必要に応じて精密検査も可能です。
一般によく知られているランドルト環による視力検査だけでなく、小児用に特化した、子供でも答えやすい視力検査を行える眼科もあります。
多く見られるのは絵を利用した視力検査で、蝶々や鳥、犬など違いがわかりやすい動物の形のシルエットを出して、なんの動物かを当ててもらう方法です。
また、左右がおぼつかない子供でもランドルト環による視力検査が行えるよう、Cの形の道具を持たせ、それをランドルト環のCと同じ向きにしてもらうという方法もあります。
このように、眼科では小さな子供でもわかりやすい様々な手法が工夫され、実践されていますので、安心して医療機関に相談してください。
また、以下のようなタイミングでは特に、積極的に視力検査を受けさせることをおすすめします。
まずは、学校検診で「要再検査」や「1.0未満」と通知されたときです。
通知を見逃さず、すみやかに眼科を受診しましょう。学校検診では詳細な検査までは行われないため、診断が必要な場合があります。
テレビやスマホの画面を見る距離が極端に近いと感じたら、典型的な見え方悪化の兆候です。子供自身は見づらいと気づかないこともあるため、親の目が重要です。
「目が疲れる」「頭が痛い」などの訴えが増えたときも目が見えづらくなっている可能性があります。学習中や読書中にこうした症状がよく出る場合は、すぐに眼科での検査を受けることが重要です。
「たぶん大丈夫だろう」「もう少し様子を見よう」と先延ばしにせず、「気になるならすぐ眼科へ」が鉄則です。視力は一度悪くなると、回復に時間がかかるだけでなく、完全に元に戻らないこともあります。
兄弟姉妹や親が近視の場合も気を付ける必要があります。近視や遠視は遺伝的な影響で出やすさが変わるため、家族に近視や遠視、弱視などの傾向がある場合は、定期的な検査を習慣づけましょう。
入園、入学、進級など新しい生活環境になったときは、検査の良いタイミングです。
見えづらくなっていても子供自身では気づかず、またごく初期では子供の挙動にもあまり変化がなく親も気づきにくいことがあります。
ですので、生活スタイルが変化するタイミングを良い機会として、眼科での視力検査を受けることをおすすめします。
また、定期的な健診と合わせて、生活習慣でも注意が必要です。近視などが発症する原因の多くは、生活環境の中に潜んでいます。
現代の子供たちは、スマートフォンやタブレット、ゲーム機など、近距離での作業に多くの時間を費やしています。
こうした近距離作業が一因であることは、さまざまな研究でも明らかになっており、日本眼科医会でも注意を呼びかけています。
また、ゲームなどで室内の遊び時間が増えることに比例して外での遊びやスポーツの時間が少なくなることも、視力に悪影響を与える要因の一つです。
これらの問題に対して、親ができることはたくさんあります。
まずは、日常生活の中で子供の目の使い方に注意を払い、適切な距離で本を読む、明るい部屋で作業する、画面を見る時間を制限するなど、基本的な生活習慣の見直しを図りましょう。
また、1日1回は遠くを見せる時間を作るなど、目のリラックスにも努めることが効果的です。目を使う作業や遊びをしたあとは目を休ませることを習慣づけるのです。
特にスマホやタブレットは顔を近づけてしまいやすく、夢中になって長時間使用してしまいがちです。そのため、使用に家庭内ルールを設けることが重要です。
「1日○分まで」「30分使用したら10分休憩」といった時間管理は、目の健康だけでなく、生活全体のリズムを整えるうえでも効果的です。親自身がルールを守ることで、子供にも自然と習慣が身についていきます。
視力の問題は学業成績や集中力にも直結します。黒板が見えにくければ授業の理解が難しくなり、学習意欲の低下にもつながりかねません。
子供が安心して学べる環境を整えるためにも、目の健康維持はとても重要な項目なのです。
また、小学校高学年以降からは予習や復習など家での学習時間を増やしていくご家庭が多いです。同時に、目をどのように休ませるかをよりしっかりと考えていく必要がでてきます。
遠くを見るなど簡単な方法だけでなく、もう少し手をかけたホットアイマスクなどのセルフケアも取り入れると良いでしょう。
さらに効率的に目をしっかりと休ませるための方法として「目リライト」がおすすめです。
「目リライト」は目の周辺筋肉に適度な刺激を与え、目の酷使によって緊張してしまった筋肉のコリをほぐすことができます。
それによって目の疲れが回復し、疲れからくる一時的な見えづらさや頭痛なども解消され、目の健康を維持することができるのです。
「目リライト」はHP上で手軽に予約をすることができますので、子供の目の健康を守るためにも一度試してみることをおすすめします。
「目リライト」はこちらから

